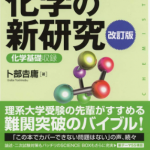こんにちは、京大農学部一回生の「ぱろり」です。
今回の記事はセンター化学についてですね、それではさっそく見ていきましょう!
私は、センター化学の勉強法は至ってシンプルだと思っています。
ズバリ、重要問題集をわからない問題がなくなるまで解くことです。
重要問題集に限らずとも、標準レベルの化学の問題集を一冊完璧にすることが大事です。
created by Rinker
¥1,623
(2024/07/26 21:08:01時点 Amazon調べ-詳細)
しかし、難関大学を目指している人であれば、基本的には二次試験対策をしていれば自ずとセンター化学も高得点がとれるようになっているはずです。
難しい問題が解けるようになるには、基礎ができていないといけませんからね。